ゲームデザイナーとしての彼の歴史と、DXの開発に関わる話をここでは紹介してみよう。
彼がゲーム業界に足を踏み入れたのはこの手のクリエーターとしてはかなり遅く、1980年台前半に故郷オースチンにて大学の講師として生活費を賄っていたのだが、その仕事が講師の増員のせいで減ってしまって金欠になり、そこに丁度友人からの誘いでSteve Jackson Gamesへの就職口があったのでそれに乗ったのが始まり。最近の人はご存知無いと思うがSJGはRPGを中心としたボードゲームのメーカーで、歴史的に残る有名なゲームを多数世に送り出した当時トップクラスのクオリティを誇った会社である。そこで幾つかのゲームの製作に関わった後、彼はTSR社に移籍。TSRとは勿論Dungeons & Dragonsの出版社であり、そこではRPGゲームTop Secret / S.Iの製作や「2nd Edition AD&D Dungeon Masters Guide」の編集に参加。その後1989年にOrigin Systems社からスカウトされて、コンピュータゲーム業界に参加する事になる。

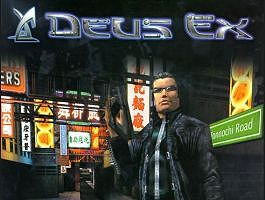

左)近年の写真 中)1999年E3でのポスター 右)System Shock
彼の最初の仕事はLord BritishことRichard Garriottの製作中だったUltima VI: The False Prophet(1990)へのデザイナーとしての参加である。彼自身が以前にプレイヤーとしてUltima IVの"徳"のコンセプトに強い影響を受けていた事もあって、この仕事でのRichardとのデザイン上の論議はその後の彼のデザイン・コンセプトに大きな影響を与えた。後のインタビューでもDXを製作するに当って最も影響を受けたゲームはUltimaシリーズであると述べている。彼が関わったコンピューターゲームとして最初に世に出たのはSpace Rogue(1989)、これはスパース・コンバットシムにRPG要素を盛り込んで当時評判になった作品である。そして歴史に残るスペース・コンバットシムの名作シリーズWing Commander(1990)では、リーダーのChris Robertsとの共同プロデューサーとしてクレジット。その後もBad Blood(核戦争後の世界のRPG)やMartian Dreams(Ultimaの外伝)Ultima VII等に関わった後に、歴史的なRPGであるUltima Underworld: The Stygian Abyss(1992)の製作に加わる。
UU1は完全なフル3D世界を動き回れるRPGゲームで、最高Detailにした時のその重さはともかくとして大きな話題を呼んだ作品である。おそらくCRPG史上の重大ゲームベスト5に数えられる作品だろう(後はWizardry 1, Ultima IV, Dungeon Master, Ultima Online)。リリースはあのWolfenstein 3Dよりも前。もっともこの作品においては彼は単なる製作者の一人に過ぎず、主な部分を作成したのはBlue Byte Production、後のLooking Glass Studiosのメンバーである。3Dプログラムを書いたのはThiefでも有名なDoug Church。次作Ultima Underworld 2: Labyrinth of Worldsでは最初から彼と組んでの製作となった(LGSに移籍の形)。
しかしながらUUはセールス的にはさほど成功せず、更なる続編の製作はOriginより否定されてしまう。そこで新たにLGSとして彼らが作成したゲームがSF世界をテーマにしたSystem Shock(1994)である。いまだにPCゲームのAll Time Bestの企画では上位に必ず顔を出すゲームであり、その先進性から大きなインパクトを業界に与えた。主人公のHackerが人類に反旗を翻した人工知能Shodanの暴走食い止めるというストーリー。如何にしてNPCとの会話にリアリティを与えるかという事から考え出されたフルボイスのE-Mailシステムや、Cyberspaceと称された独特のゲームI/Fは高いオリジナリティを持っている。私もこのゲームはリアルタイムではプレイしていないが(当時の他のOriginのゲームに比べるとほとんど目立たなかったと記憶している。インターネットが無い時代であり、特に日本では日本のゲーム誌に取り上げられなければ情報が入ってこないという時代だった)、今見てもI/F系などは当時の他のFPSと比べると非常に斬新である。どこからこんな発想が出て来たのかと言う意味で”異端”という感じすらする。現在System Shockをプレイした事があるプレイヤーの数は少ないだろうが、Spectorがこの作品で生み出した新操作”Lean”は、今やFPSゲームには欠かせない物となっている。またDX 2ではプロデューサーにまでなったHarvey Smithとは、このゲームのテスターとして彼が参加したのがキッカケで知り合ったそうである。
その後SpectorはWings of Glory(1994), Cybermage(1995), Crusader: No Remorse(1995)といった有名な作品にプロデューサーとして関わり、その後再びLGSのDougと新たなプロジェクトに取り掛かる。しかしながらその作品Thief: The Dark Project(1998)においては彼の名はSpecial Thanksに記されているだけである。彼はDougと「これからのゲームはどうあるべきか」について長期間議論を交わしていたそうだが、デザイン面では意見の不一致があったそうだ。
そうこうしている内にLGSのオースチン支社が閉鎖される事となり、彼はその場に残って自分自身の小さな会社を設立する方向で動き出す。かつて同じ仕事をしたLGSのメンバーでオースチンに残る者を数人スカウトして、まずはゲーム界への足掛かりとして”Lancers”というシンプルなアクションゲームの企画を製作する。ところがこのゲームは20以上のPublisherにて断られ、全ての会社からSystem Shockの様な画期的なRPGを作成するべきではないかという意見をもらったそうだ。とはいえそう言ってくる会社側も、全くの新規なアイディアのゲームを作成するには予算が倍以上掛かる上にリスクが大きいという事で、実際に自分達との契約をしてくれた訳ではなかった。その内に新しいタイプのゲームとなるコードネーム”Manifesto”の企画を煮詰めて、某社と何とか契約寸前まで行った所でオファーをよこしたのがIon Stormである。連絡を受けた時点では既に相当な苦労をして契約までこぎつけていた為にあまり気乗りはしなかったそうだが、いざJohn Romeroを始めとするIonの人間に会った際に提示された条件は「到底他の会社や自分達では獲得出来ないほどの莫大な予算と、何でも自分達の好きにやって良い」という破格の物であり、急転直下彼は1997年にIon Stormのオースティン支社へと数人の仲間と共に赴任する事になった。
その後彼をスカウトしたJohn RomeroはDaikatanaの悪評と共にIon Stormを去る訳だが、Spectorは彼に対しては非常に感謝をしているそうで、「多額の予算を与えて自由にやらせてもらえる環境があったからこそDeus Exは完成出来た訳で、こういったスポンサー的な役割を果たしてくれる人間がゲーム業界には必要である」と述べている。



左)Ultima VI 中央)Wing Commander 右)Ultima Underworld
Deus Exの基本コンセプトは1994年に遡る。UU2リリース後から彼は新しいタイプのゲームの構想に入り、1994年にはOriginに対してTroubleshooterというゲームの企画を提出している。この企画書によると舞台は現代社会で、主人公は元警察のSecurity Specialist。非常に高度な機密に属する仕事を政府から請け負って解決に当たるというFPSゲーム。ミッションベースで構成されており、事前に与えられた様々なデータから侵入経路等を決めて、人質救出やハイジャック犯の逮捕等を行うという自由度の高い物。企画書には同時にプロジェクトのリスクは非常に高いが、まだ誰も実行していない企画故に他社に先行してやるべきと書かれている。
しかし結局このゲームはOriginのGoサインをもらえず、このゲームの企画は彼の頭の中に残されたままとなる。その後LGSとの間にJunction Pointというゲームの企画が有ったらしいがこれも陽の目を見る事は無かった。彼はこの件に関してスポンサーが理解を示さなかったのは勿論だが、テクノロジー的に自分の考えているレベルの事をゲーム内で実現するには現状では無理があるとも考えていた。1997年に彼が記述した仮想のRPGゲーム”Manifesto”のアイディアである「The Rules of Role-Playing」には、この時点での彼の考えるゲームのコンセプトがまとめられている(幾つか抜粋)。
*常にプレイヤーには明確なゴールを示せ。何をすれば良いのかを曖昧にするな。
*パズルを作るな。ゲームはデザイナーが考えた事をプレイヤーが推理する物ではない。常に複数の突破方法を用意せよ。
*強制的な終了を避けよ。プレイヤーがある種の失敗をした事でゲームがやり直しになるような設定を作るな。プレイヤーが取ったどんな行動でもゲームがそのまま進むようにデザインせよ。
*Players do; NPCs watch. 全ての行為はプレイヤーに行わせよ。もしNPCが魅力的な行動を行うシチュエーションが有るなら、それをプレイヤーにやらせるようにせよ。
*プレイヤーには常に報酬を与えよ。それはゲームの進行に際してプレイヤーが魅力的に感じる物が望ましい。
*それぞれのロケーションは立体的に結合せよ。単独の接続点しか持たない場所は避けよ。
やがて彼はIon Stormに引き抜かれてDXの製作に取り掛かる訳だが、その際にDXというゲームの為に作成しなおされた物が以下の条項。
*全ての解決すべき問題には常に複数の解決方法を持たせる
*戦闘には武器の能力ではなく、作戦が物を言うデザインに
*出来る限り早く何を達成すれば良いのかをプレイヤーに示す。それによってプレイヤーには複数のルート選択が生まれる。
*ある場所への到達方法には複数のルートを設ける
これらを元に最初の半年は実際の製作には取り掛からず、企画会議のみで内容を煮詰めていった。当時のコードネーム”Shooter”と呼ばれるそれは、背景設定等コンセプト的にはDXを思わせる物だが、明確なミッションベースの構成である等若干の違いが見られるし、ゲームシステムの具体的な点はほとんど決まっていなかった。その後も現実に起こったとされる事件(ケネディ暗殺やArea51等)や歴史上の秘密組織等の背景研究を続け、そして実際にAugmentationやSkillのシステムが考え出されてゲームが企画として形になったのは1998年の3月の事。ここから本格的なゲームの製作がスタートされる。当初企画の段階では6人だったスタッフは20人にまで増員された。
初期段階で重要なコンセプトに関する決定も行われた。まずは「ストーリーを完全なリニア(一本道)な物にする事」。当初プレイヤーの行動によって幾つかに分岐するタイプの構造を取るという案も有ったのだが、内部で取れる行動に多様性を持たせる事でストーリーがリニアな点はカバー出来るという事からそう決められた。「我々が関知するのはプレイヤーがある障害を突破したという点のみで、それを如何にして突破したかは問題にしない」。
次に非戦闘要素の導入。戦闘部分に特に力を入れず、それを回避出来る様なSkillやAugsを大幅に取り入れるというデザインに。「RPGは戦闘が無いと面白くないというのは誤解であり、それ故戦わないとならないという要素は出来る限り排除した」。
そして”Deus Ex was a game of problems (not puzzles)”という条項。「RPGはプレイヤーの体験が全てであり、如何に面白い設定やミッションをデザイナーがゲーム内に盛り込んだかは二次的な要素である。デザイナーが用意した解答をプレイヤーに見付けさせるゲームではなく、プレイヤーが自分で解答を見付けるゲームとしてデザインした」。
しかし企画では案として取り上げられたが、実際の製作に入った段階でハードウェア&ソフトウェア的に現段階では無理とされた事項も有る。彼がゲームを語る時によく出てくる言葉に"Deep Simulation"という物がある。これは現実世界をどれだけリアリティを持って再現出来るかというコンセプトで、具体的には「プレイヤーの行動に対するNPCのリアクション」・「リアリティを持った臨機応変に対応出来る会話システム」・「世界に存在する様々なObjectに対して多様な形でインタラクト可能」といった点になる。これらに関してはかなり限定的な部分しかDXには取り入れられていない。最後のObjectに関してはある程度の成果をゲーム内では見る事が出来るが、その他に関しては満足の行くものではなかった。このNPCの自然なリアクション、会話におけるAIシステム、Objectの物理シミュレーションに関しては、DX2にて重点を置かれて開発されている。
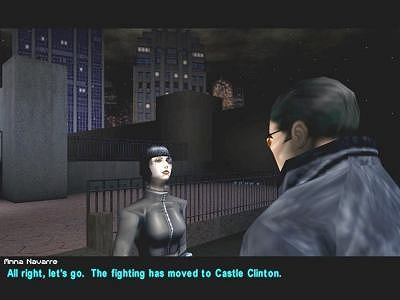

左)初期のAnnaのデザイン 右)初期のSS
実際のゲームの製作は当初はそれほど順調ではなかった。まず選択したUnrealエンジンが自分達の望む事をどの程度まで実現可能なのか、まずはそれを掴むまでに半年以上掛かったと言う。DXのデザイン自体がテクノロジーに強く依存した物である為に、その過程でかなりの部分が実現不可能という事で切り捨てられた。例えば当初のアイディアでは非常に細密な構造のインドアや広大なアウトドアエリアを考えていたが、現実のエンジンのレンダリング能力ではそれは不可能という事で修正を余儀なくされている。
次にSpeactor自身は熱心なTRPG(テーブルトーク)のファンであり、その経験から生み出された紙の上の企画段階では上手く行くと思われた物が、ゲームにしてみると上手く行かないというケースが多々有ったと言う。最初のプロトタイプMapが完成された段階で、彼は長年仕事を共にして来たDoug Churchを始めとするLGSのメンバーにプレイテストを依頼しているが、この時共通して帰ってきた感想は「詰まらない」という物だった。この時点でのDXのキャラクタは非常に静的なパラメーターを持った存在として設定されており、CRPGとして動かしてみるとダイナミックさに欠けて緊張感が無いというのが問題となった。そこでSkillとAugsのデザインはHarvey Smithの手によって全面的に今の様に修正される事となった。具体的にはそれぞれにレベルを設けて、適用には時間制限とリソースを必要とするという物へと変更された。
またSpector自身が正しいと信じ込んでいた当初の企画の内容もある程度の変更が行われている。彼はMapを出来るだけリアリスティックに作成する事が重要と考えていたが、テスターの反応ではゲーム内のロケーションは現実に則してリアルであるよりも、ゲームとして面白い構造である方が良いという意見が多かった。また彼はRPGで重要な物は人間(NPC)とのインタラクトであり、モンスターといったキャラクタはゲームに必要無いと考えていたが、これも内部の反対意見によって数種類のモンスター(生物)がゲームに採り入れられる事となった(最も意外な変更事項だったと感想を述べている)。
その他のゲームのデザインに関して。「プレイヤーがゲーム内のI/Fにアクセスした時にゲーム内の時間をリアルタイムで進めるか」については、よりTacticalな方向性を打ち出す為にSystem Shock 2の様なリアルタイム制は取り止めた。「プレイヤーキャラにプレイヤーが名前を付けられるようにするか」に関してはかなり揉めたようで、RPGである以上は名前を付ける事は許可したいがそうすると会話ログが上手く働かない。そこで妥協案としてコードネームはJ.C.Dentonで一定だが名前は一応付けられるという風に設定された。同じく最初の案ではJ.C.に関しては性別の選択も可能だったが、ボイスを2倍用意する事になるので取り止めになった。ちなみに名前のDentonはSpectorの友人から来ている。
それからのDXの製品発売後の評判等については特にここでは記述しないが、最後に彼の語るゲーム完成後の反省点について書いておこう。
まず長い目で見ればUnrealエンジンの採用は成功だったと述べている。ほぼ80%の部分はライセンスした物をそのまま使う事が出来て、プログラマーと開発期間の大幅な短縮につながった。特にMapをデザインするEditorの出来は素晴らしく、プログラム記述部分のUnrealScriptも優秀。しかし一方で自分達が製作した物ではない為に完全に使いこなすという段階までは到達出来ず、特にAIに関してはかなり不満の残る物となってしまった。
次に戦闘に偏ったゲーム性になってしまった点は大きな悔いが残るそうだ。非暴力を心掛けてもどうしても殺さないと先に進まない個所も有るし、この辺の自由度には不満が残るという事だ。これは本来のデザインでは”会話による解決”という要素を多くのシチュエーションにて取り入れたかったのだが、そこまでのシステムが完成しなかった事に原因がある。会話時の取引きや交渉によって解決策を見付けられるという要素がAIやスクリプトの限界で大して盛り込めなかった。
それとゲーム中のI/Fに関して。御存じのようにDXはPS2に移植されており、その移植は直接Ion Stormが担当した。その際パッドでの操作に対応させる為に全面的に操作体系を見直す必要に迫られ、なるべく負荷を掛けないような操作性を模索していた所、これまで当たり前と考えていたPCのKBを使った操作に如何に無駄が多いかに気が付かされたとコメントしている。PC版のデータにアクセスする操作部分には無駄が多く、ここはDX2では全面的に修正したいと述べている。
TOP
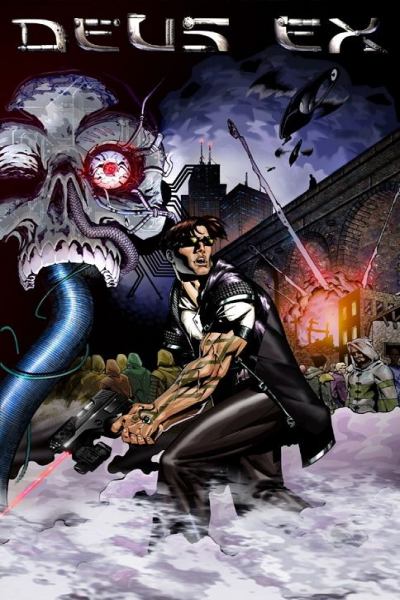


左)初期の宣伝ポスター 中央)Dentonの最初のArt 右)Guntherの最初のデザインArt
<BACKSTORY>
以下若干のネタバレを含むので未プレイの方は注意。
◎Map名をみてお気付きの通りにDXでは最終的にはかなりの部分が製品版からは削られている(例えば07と13という通し番号が存在しない)。様々な情報からすると、分かっているいる範囲での削られたロケーションはインド、テキサス、ワシントン、そして宇宙ステーション。
◎Bob Pageは最初の案では強力な(Aug&Skill)パワーを持ったボスとして設定されていたが、そういった在り来たりの設定では詰まらないという事で一般的な意味でのラスボスとしての位置付けでは無くなった。その為ラストは戦闘に関して言えば大して難しくは無くなっている。
◎Skillに関しては会話の際に有利な情報を聞き出せる為のカリスマ、Inventoryの数を増やせるStrengthといった物が当初は存在していた
◎Paulは主要なキャラクタであるにも関わらず序盤にて姿を消してしまう。これはお分かりのように彼がNYにて死んでしまう可能性があるので後半のMapにて重要な役割を任せる事が出来ないからなのだが、これに関しては結果としてあまり製作側もその使い方に満足していないようだ。
◎一見して練りに練られたストーリーのDXだが、キャラクタの登場シーンに関しては最後まで決まらない部分が多かった。死亡の可能性があるキャラを後半のMapでどう調整するかとかギリギリまで決定しないケースもあったようで、例えばGuntherは半分位でゲームから消えるという設定になっていた。Anna Navarre, Walton Simonsが殺さないと繰返し出て来る構成も最後に付け加えられた物。
◎一番最初に解除するパッドの4桁の数字はSystem Shock 2の最初の解除コードと同じである
◎NYにてバスケットのゴールにボールを入れるとメッセージが出る(System Shock 2と同じ)。これはSpector自身が大のNBAファンである事に由来している。
◎Everret宅に存在するAI(Morpheus)とJ.C.の哲学的な会話に付いてだが、当初のアイディアではこの部分をテキスト入力式の問答プログラムにするつもりだったそうだ。プレイヤーが実際に思う事をテキストで入力した物を解析して、それに対する反応を実際にMorpheusにしゃべらせるというシステム。時間的に満足の行く物が出来なかったので見送られたが、将来(DX2?)実現したいアイディアという事だ。
Q:Morpheusのパートは他との絡みが大きい訳ではなく浮いた感じがあり(ラストのプレイヤーの選択に影響を与えるかという程度)、これはゲーム上どのような意味があるのか、或いはあったのだがそのパートがカットされたのか?
A:元々それほど重要な意味合いがあった訳では無く、EverettとIlluminatiの哲学を紹介するという目的で作成されたパートだった。しかしその後会話の内容は拡張されて、このゲームの意味する所を深く論じる為のパートとなった。
Q:DXではマルチエンディングを取っているが、この決定は最後の最後にプレイヤー自身が選択出来るというシステムになっている。またその決定にはそれまでのゲームのプロセスはそれほど影響しない。これをもっと早い段階から「プレイヤーの行動による結果としての分岐」にした方が良いという考えはなかったのか?
A:当然両方の考えは案としてあった。しかしながら我々のこのゲームに関する基本コンセプト(哲学)は”micro decisions”という言葉に集約される。これはあらゆる場面において複数の解決方が存在するという事で、固定された方法でのクリアしか存在しないというケースを出来るだけ避けるという意味になる。その意味でプレイヤーが最後に来た時点で、それまでの経緯によって既にEndingが決定されているというのはポリシーに反するという事でこういう形態にした。
TOP