
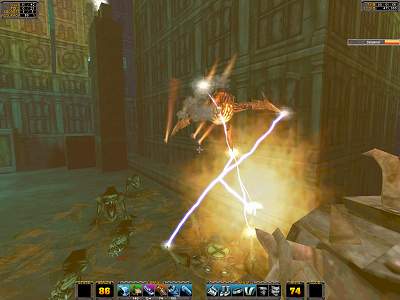


| HORDE |
| KPCの最大の特徴であり、売りにもなっているのはHorde(大群)テクノロジーである。画面上に数十体の敵モンスターを同時に出現させてもフレームレートが大きく低下しないという自社開発の技術で、これにより大量のモンスターとの戦いを可能にしている。またそれと併せてスポーナーと呼ばれる装置が導入されており、これはスクリプトやプレイヤーが近付いたりして作動すると開いて、その内部からモンスターがテレポートして出現してくる。一定のダメージを与えて機能を停止させないと無限に出て来るので、出現する箇所では戦い方を考えないとならない。大量出現はこのスポーナーを使う事もあるし、オーソドックスに敵が沸いて出てくるケースもある。 この様なモンスターを大量出現させるゲームとしては、Serious Samシリーズがあまりにも有名である。しかしこのKPCはその発売の前年に出ている訳で、それならばこのHordeがもっと話題になっていても良いはずである。しかし発売当時においては大して話題にもならずに消えていったゲームであり、では何が不味かったのかを成功したSSとの比較で順に見ていきたい。 まずはシンプルな比較としてSSほど大量には敵は出現しない。難易度が上がると敵が増えるらしいので何とも言えないが、Normalでのプレイではせいぜい多くても30体位で、通常は20体位までという程度。だから凄く沢山の敵が出て来るという強烈なインパクトは感じられなかった。ただ私自身はSSの方をプレイしたのが先であるという点は考慮する必要があるし、30体でも同時期比較としてなら十分な数とも言えるので、ここは決定的な問題点ではない。また出現時のフレームレートについても、確かに大きな低下は見られなかった。 第一に問題なのは敵の種類で、全てのタイプの敵が満遍なく大量に出現するのではなく、Hordeと名付けられた状態で大量出現するモンスターは基本的に2種類のみである。例えばスポーナーは固定された一種類の敵を生み出すが、その九割五分位は一番の雑魚敵であるHeadlessとStump(小さな恐竜)であって、他の敵がスポーナーから出て来る箇所はほとんど存在しない。この2種類が大量に出るシーンに、その一つ上ランクの敵ならば5体前後、更にその上の中堅クラスならば2〜3体がミックスされて出て来るというのが基本パターン。SSの様に下から上までが組み合わされて大量に出て来るという事は無い。よって「確かに敵は大量に出るが、その大半は弱いタイプである」、「中堅以上の敵が数多く出て来る事はほとんど無いので、敵の組み合わせパターンも単調である」、という風になってしまっている。 なんでこうなっているのかと言うと、それは全体でのバランスの調整に関係している。KPCでは普通のFPSの様に進むエリアもあれば、大量に敵が出現するエリアもあるという構成なので、プレイヤーの持つ武器の総合的な火力(威力+弾薬数)はそれ程高くない。大量に敵が出現する方に合わせて火力を調整すると、敵の数が少ない普通のエリアでバランスが崩壊してしまうからだ。つまり普通のエリアでの戦闘においてバランスを保つ以上はプレイヤーの火力は高く出来ず、その設定で2種類以外の敵も同時に大量に出て来るようにしてしまうと、プレイヤー側が到底太刀打ち出来なくなるので数が制限されているのである。SSでは敵の数や強さに見合った火力をプレイヤー側に持たせているので、敵の出現数を大量に出来るし、その組み合わせにもバリエーションが可能になる。(逆に言えばSSでは少ない数の敵が出てくるシーンは簡単になり過ぎるので作り難い)。 第二に戦闘エリアが狭い。SSはアウトドアを中心に広い戦闘エリアを確保し、プレイヤーが逃げ回ったり敵を誘導したりと動きの自由度が高く、それが大量の敵との組み合わせに上手くマッチしていた。ところがKPCではマップサイズは普通のFPSと変わらないので、大量に敵が出るエリアでは「逃げ場が少ない」上に「敵が邪魔して動きにくい」という事になっている。その為にゴチャゴチャした状態での戦闘になりがちであまり面白くない。 第三に敵の出し方が不味い。敵が空間から沸いて出てくるという設定は一緒だが、SSではエリアが広い分、後方等の視界外に出現したモンスターが実際にプレイヤーの場所にやって来るまでに若干の間があるので対処も可能だった。しかしKPCでは前方に出現するのと同時に、クリアしてきた後方のそれもプレイヤーのすぐ近くに突然沸いて出るので、ほとんどのケースでは背後から攻撃されて初めてそれに気が付くという風になっており、これではゲームとして面白くない。 第四にアイテムの配置の仕方が悪い。無敵, ダメージ増加, HP上昇等のパワーアップアイテムが存在しており、こういったアイテムは過剰に敵を出現させる際にバランスを保つ物として有効である。だがKPCではその置き場所自体が解り難いエリアが多々出て来る。SSでは解り易い場所に置かれている事がほとんどだし、プレイヤーが取るタイミングを計ったりも可能である。反対にこのゲームではオブジェクトの陰やマップの隅に隠されていたり、簡単には到達出来ない場所に在ったりで問題あり。必死になってリトライしてクリアしたら、その後のアイテム回収時にパワーアップアイテムを発見して、インスタントアイテムなので持っても行けずに損をするといった事が何回もあった。もっと酷いケースでは、そのエリアでの激戦用に配置されてはいるのだが、シークレットに置かれているのでそれを解いてからでないと入手出来ないというのまである。 なのでそのゲーム構造を理解してからは、敵が多く出るエリアでは最初(or数回)の対戦は敵を倒す事は諦めて、マップ内を走り回ってパワーアップが何処かに置かれていないかを確認し、それからロードして本格的にチャレンジするという形に切り替えざるを得なかった。携帯式ならば好きな時に使えるので良いのだが、インスタントタイプのパワーアップの方が多い。結局この様にパワーアップアイテムを見付け辛くしているという設定は面倒さを増しているだけであり、面白さを殺ぐ要素になっている。 更に大量の敵の出現時に頻繁に使われるスポーナーも、あまり効果的な存在にはなっていない。作動した瞬間にプレイヤーから位置が見えているケースでは、すぐに撃たれて止められてしまい効果薄だし、またそれだと敵が大量に出ないので意味も無くなる。よって比較的解り易い位置に置かれているケースでは、スポーナーが複数在るという設定が多い(最大で6個同時位)。しかし通常は作動した時点ではプレイヤーからは見えない曲がり角の先等に置かれるパターンが最も多く、この敵の出現の仕方はスポーナーではないかと考えたら、先に進んで確認しないとならなくなる。 スポーナーの耐久力はそこそこ高いので、破壊にはショットガンかグレネードランチャーを使うのが効果的。キャラクタによっては打撃武器も有効となる。敵が次々に生まれてくる構造上、ショットガン攻撃だと離れた場所から撃っても出現した敵が間に挟まって防壁になってしまうので、間近まで行って撃つのが効果的となる。グレネードランチャーならば遠方からでも上手く当てれば一発で閉じられる位に効果的なのだが、跳ねた敵や大型の敵の弾に当たっても爆発してしまう為に、即死級のスプラッシュダメージが降りかかったりする危険性を持っている。 スポーナーだけならともかく、他の敵とミックスされて出されるケースでは、一般の敵の相手をしていてもどんどん敵が生まれてしまうし(制限はあると思うが)、そのスポーナー側からの敵の攻撃にも対処出来なくなる。よってとにかくまずは全速力で全てのスポーナーを止めに掛かるという手段しか実質選択肢が無く、何時でもそれではやっていても面白くない。これが第一の問題点。こういった“プレイヤー側が止められる無限沸き”という設定はGears of Warとか他のゲームでも見られる要素だが、大抵はどうやって対処するかというプレイヤー側の行動に多少の自由度が設けられているのが普通で、常に強引な突破でスポーナーを止めに行くという対応策しか無いのは欠点である。 第二の問題は装置が見えていない状態で、そこに到達するまでに狭い廊下や通路を通らないとならない場合、その通路が敵で埋まってしまい、やって来る敵を蹴散らしたり、上をジャンプで強引に越えてそこに到達しないとならなくなる点。HeadlessはともかくStumpの方は火を吐くので、避けるスペースが無い通路での強引な突破にはそこそこのダメージは覚悟しないとならない。特に複数のスポーナーが同時作動するエリアではノーダメージでの突破は困難であり、よってその時点でHPが相当低い状態だと詰んでしまう恐れがある。つまり一般的なアクションFPSに比較して、HPが低い状態でデッドエンドに陥り易いゲームとなり、かなり戻ってのやり直しを余儀なくされたりする。この点はやはりHPが危うくても上手く戦えば突破出来る可能性を残した設定のゲームに劣ると言えるだろう。 逆に広いエリアを通ってスポーナーに到達可能なケースでは、やり易くはなるが単調で簡単になってしまう。打撃武器等で敵を適当にあしらってからスポーナーを破壊するという単純な作業になるので、それが続いても戦闘として楽しくならない。それなら適当な数の敵を、スポーナーという一箇所からではなく周囲から出現させた方がマシである。 総合的には敵を大量に発生させるというメインの要素が大して面白さに繋がっておらず、それがこのHordeテクノロジーが評判にもならずに、またゲームの評価の方も高くならなかった要因の一つである。当時の他のFPSとの差別化という観点からは意味がある物とも言えるが、あまりそれにこだわらずに、もっと限定されたエリアでのみ大量発生を用いた方が面白くなったのではないかと思える。 |

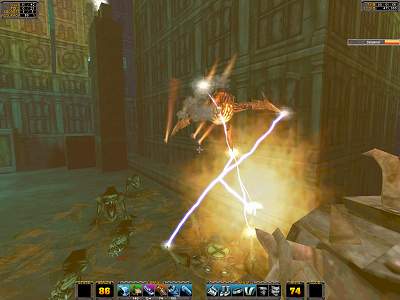


| COMBAT |
| 武器は全12種類登場するが、各人が持てるのはその内6種類で、またメインで使用する4種の基本武器は全エピソード共通なので、実際の感覚としては武器種類は少ないという感は否めない。2ndary Fireを備えている訳でもないので、この攻撃方法の少なさはアクションFPSとしては大きな問題点と言える。弾薬はそこそこある方だが、敵の数も多いので存分に撃ちまくれる程ではない。各人の打撃武器がかなり強いので、Hordeの雑魚敵相手には積極的にそれを使って弾を節約するのも大事となる。使い分けがハッキリしているので特定の武器の弾を切らさないようにローテーションでの使用も効果的になるし、またシークレット他のマップ探索を行って弾の回収に努めるのも、特に後半のチャプターでは必要になってくるだろう。 マップの雰囲気等は各エピソード毎に変化すると書いたが、その一方で敵の種類については工夫が見られない。全てのエピソードにおいて出て来る敵の種類はほぼ同じなので、戦闘の感覚はあまり変化しない為に単調である。15種類程度出て来るが、長丁場を持たせるほどにはバラエティに富んでいない。私としてはこの点がゲームの最大の欠点だと思える。飽き易いと言っても良く、率直な意見としてこれを最後までプレイした人はどの位の割合なのかとも考えてしまう。もし敵のAIが優れているなら楽しめるのだが、それについては普通で特に目立ったレベルでは無い。 難易度は最初の2つのエピソードは普通。HPが十分にある地点でクイックセーブしておいて進み、ミス等で高いダメージを受けてしまい、現在のHPでは突破が困難な状態になったらロードしてやり直すというオーソドックスなやり方で問題無く、難易度としても易し過ぎず難し過ぎずで適度に調整されている。繰り返しトライしてもクリア出来ないような箇所は出て来ない。しかし後半のエピソードは難易度が高くなり、EP3の後半のチャプターと、EP4では全般的に相当な難しさである。どんなゲームでも段々と難しくなっていくのは当然だが、これはもう難易度Normalとは呼べないだろうという位に難しくなるので、その急激過ぎる難易度上昇は問題点の一つとも言える。 *中堅クラスの敵が堅く、当たり所にもよるがショットガンやグレネードランチャーでも3〜5発程度は必要 *敵の攻撃による被ダメージが高めの設定 *集団に対してのグレネード攻撃となるJack-in-the-boxのダメージが低くて効果が薄い *回復アイテムの配置が偏っており、足りなかったり逆に余ったりでバランスが悪い(戻ったりして回収する事もしばしば) *物陰に隠れている敵が突然目の前に出て来るというやり方や、背後のすぐ近くにスポーンしての不意討ちがよく使われる 難易度が高くなる基本的な原因としては上記の様な点が挙げられる。2つ目のエピソードまではそれでもあまり気にならないのだが、敵が増えてくる後半のエピソードでは問題となってくる。 他の要因としては、敵の弾にこちらを追尾するタイプが多いというのも含まれる。直線的に飛んで来る弾や突っ込んでくる敵をかわしながら戦えるのならば良いのだが、このゲームではBaldemastersの手裏剣, Unipsychoの発する炎弾, Fat Ladyの投げる腐肉等が、こちらを追尾して襲って来るので避けるのがより大変になる。障害物に隠れられて安全な逃げ場が背後にあるのならば、壁等に誘導してぶつけて避けたりも出来るのだが、オープンなスペースでの戦闘になると避けるのに苦労するし、そちらにばかり気を取られていると他の敵からの攻撃を受けてしまう。特にUnipsychoの炎弾は本当に厄介な代物で、早急に倒そうにもタフなので余計に始末が悪い。他には障害物を越えて到達する衝撃波を放つ敵や、障害物に隠れない限りは回避出来ない広範囲攻撃を繰り出す敵もいたりして、それが他の敵とミックスされたりすると更に大変になる。 それとBallbustersの存在。高速で飛ぶ砲丸を撃って来る敵になり、当たると高ダメージを受ける上に跳ね飛ばされてしまう。居る場所が先に分かっているならば対処も出来るのだが、後半からはスナイパーの様に高所に配置される事が多くなる。その配置が嫌らしいというか極悪なのが難易度を上げている原因。例えば足場の狭い場所で他の敵と戦う際に上方から攻撃してくるので一発で跳ね飛ばされて落下死したり、撃たれたのに気が付いてその一人目を避ける位置に逃げると、そこを狙う二人目三人目が別に設置されておりそれに攻撃されたりという事もある。或いは通ったドアの後方上空からいきなり撃たれたりや、スポーナーを止めに行って近付いた際に死角の上方から撃たれたりと、注意が向かない方向からの攻撃という配置を知らないと対応が不可能という状況が多い。よって死にながら配置を憶えるしかなく、それが連続するのではいくら何でも酷過ぎるという感想しか出て来ない。しかも攻撃するには弾が弾き返されてしまう腹の的以外を狙わないとならない上に、左右へと頻繁に動き回ったりもするので、遠方に居ると落ち着いた場所以外からでは倒すのも難しい。 後はプレイヤーが動き回る戦闘エリアにて、壁から定期的に炎が吹き出しているので動きながらもそれを避けないとならないとか、弾を吐き出して攻撃してくる魔法の口?の射線を避けて動かないとならないとか、(タイマー等のガイド無しで)一定時間内に先に進めないとゲームオーバーになる箇所とか、敵以外の障害が用意されているエリアも難しさを増している。 まとめると難易度が高いのはともかくとして、死にながら憶えるしかないエリアがずっと続いたりとか、ストレスになる難易度上昇要素が含まれているのが問題点。SSの様に正攻法で戦うタイプのゲームでは難易度の高さも良いと思うのだが、KPCでは理不尽な設定に起因する難易度の高さであり、それがマイナスに働いているという印象。それと同一難易度でのプレイにおいては、もっと難易度バランスを全体で統一するべきだろう。ただし単調なゲーム性に変化を付けるという意味では、難易度の上昇は多少の効果を挙げているとは言える。 続いては逆の意味で問題になっているアイテムについて。携帯可能なRage Orbという一分間弾数無制限になるアイテムが有って、どうしてもショットガンやグレネード弾が大量に欲しいというシチュエーションでは重宝する物になる。また弾を全く消費しなくなる為に、弾を大量に消費する最強武器と組み合わせると破壊的なまでの威力を発揮する。HPには影響しないので万能ではないが、現在のステータスではクリアが無理というエリアでも、これを最強武器と組み合わせて連射する事で突破が可能になったりもする。よって非常に重要なアイテムとなり、これだけはシークレットに在るなら(見えているなら)、時間を掛けてでも回収しておくべき物と言えるし、いざという時用に一つは温存して置いた方が良い物でもある。(多分各EPに2〜3個位だと思う。Black Diamondsの昇格は除いて。) これの何が問題なのかというと、エピソード最後のボス戦で使うと強過ぎてアンバランスになってしまうという点。大量の敵が散らばっているケースではまだしも、ボスという狙うべき敵が特定されている状況では、一分間の最強武器撃ちまくり攻撃はあまりに強過ぎる。ボス戦はセーブが出来ないという縛りがあるものの、個人的にはEP1, 2, 4では初回トライで呆気なくクリア出来てしまう位だった。ボス戦には持ち込めないとかにしておくべきだったのではないか。 最後に書き残した点を幾つか。AIはスタックしたり、壁に向かって走ったりもあり。特にHorde系の2種類の敵に多く見られる。こちらが上手く障害物に体を隠したりすると一方的に攻撃も可能。また自分の攻撃が障害物に邪魔されて当たらなくてもそのまま撃ち続ける。 敵の体の一部は損傷して取れたりもするし流血も結構派手だが、こういったバイオレンス系の設定は4段階に調整可能。 バグとしてはオブジェクトへのハマリで動けなくなる事が何回か発生した。しゃがみで外れるケースもあるが、駄目ならやり直すかチートで抜けるしかない。 |


| GRAPHICS |
| LithTech 1.5をライセンスして使用。ただしこれがNo One Lives Foreverに使われているLithTech 2.0よりも劣っているという訳では無いとしている。1.5をライセンスしてからエンジンを大幅に改造しており、いわば両者は異なった方向で進化を遂げたLithTech
Engineである。つまり使われているのはテクノロジー的には2.0相当のエンジンであって、公式の2.0版をライセンスしてその機能を導入する必要性は特に感じられないし、改めてライセンスし直しても修正に時間が掛かってしまうので止めたそうだ。 大量のモンスターを描画するHordeテクノロジーについては一応の評価は出来るが、それ以外は突出した所は無いグラフィックスである。当時のレベルからすると水準以上ではあり、エフェクト系は結構綺麗ではあるのだが、例えば同じLithtech Engineで同年発売のNOLFとの比較では向こうの方がクオリティは高い。ただサーカスがテーマとなっており色使いがカラフルなので、その点が見た目の綺麗さにプラスとして働いているというのはあると思う。 ワイドスクリーンには未対応。グラフィックスの設定項目はかなり多く、相当細かく調整が可能である。 |
| SOUND |
| 3Dサウンドに対応。Direct Sound 3DのSoftwareとHardware、それとA3Dに対応している。EAXのサポートはパッチで導入という話だったのだが、実現しなかったようだ。それとシチュエーションの変化に応じてダイナミックにBGMが変化するDirectMusicに対応しているが、逆にそれがDX8以降のバージョンでの互換性破壊によるBGMの再生問題を引き起こしているらしい。 BGMにKISSの音源はほとんど使われていない。会社の音楽担当が作ったBGMが流されている。その理由は第一に、制作に当たってKISSのファンの意見を聞いた結果、「FPSをプレイ中にバックにKISSの音源が鳴り続けているのは合わない」というのがほとんどだったから。第二にゲームの背景はコミックブックの方のダークな世界観なので、バンドとしてのKISSの楽曲とはイメージが異なるという点。結果的にKISSの曲はジュークボックスを操作すると流れたり、限定的なイベントシーンのみで使われている。クレジットされているのは以下の曲。 God of Thunder, Psycho Circus, Unholy, Rock and Roll All Night, Cold Gin, Love Gun, God Gave Rock & Roll To You, Shout It Out Loud, Detroit Rock City しかしそういった理由があるにせよ、一応ゲームのタイトルにも有る訳だし、もっと音源使用の場を増やすべきではなかったかと感じられる。オリジナル制作のBGMの種類はそれ程用意されていないので尚更。 |
| MULTIPLAYER |
| 普通のデスマッチと、倒した相手の成績によって入るポイントが異なるバリエーションの2種類のみ。試していないので評価は出来ないが、当時も人気は無かったと記憶している。またこの時代のLithtech
Engineはネットコードの面でも、Quake, Unrealの両エンジンに比較して問題があった。 |