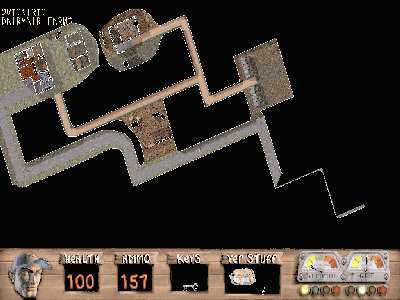

| シ ス テ ム |
キャンペーン 難易度はWuss / Meejum / Hard Ass / Killbilly / Psychobilly の5種類。最後のPsychobillyではセーブが出来ない仕様。ゲーム途中での難易度変更は不可。リプレイはエピソード単位で、個々のレベルを呼び出す事は出来ない(コンソールコマンドでの呼び出しは可能)。 セーブ&ロード セーブはマニュアル方式で回数に制限なくどこでも行える。クイックセーブもあるが、単にメニューが出て最後にセーブしたスロットが表示されるだけであり、通常の意味でのクイックセーブはサポートしていない。オートセーブは無しで、死亡後にそのレベルの最初からやり直す事は可能だが、武器関連は全て無くなってしまう。よって定期的にセーブしておく事が大事。 OBJECTIVES 具体的な指示は出ないが、鍵を探して進めるだけなのでその点は問題無い。Build Engineの持つオートマップ機能はこのゲームでも同じ様に使用出来る。 EXTRAS 喋る台詞をより下品&ユーモラスに変更するCuss Packというアドオンが用意されている(原則無料)。 英語 字幕機能はなし。クリアには英語の理解は特に必要無いが、ユーモアを存分に味わうには英語が理解出来た方が良いというゲームである。 |
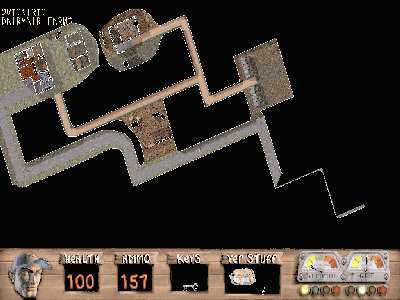

| GAMEPLAY |
| エピソードはOutskirtsとDowntownの2個で全15レベル(定番のシークレットレベルは無し)。どちらからでも始められるがDowntownの方が難易度が遥かに高く、更にそれがエピソード最初のレベルからとなっているので、順番にOutskirtsの方を先にクリアして武器やアイテム類を持ち越しで始めた方が無難。 難易度Meejum(Medium)で12〜15時間程度の長さ。レベルは初回プレイで30〜40分程度の物が多いが、中には2時間クラスの巨大な物も含まれているのでこれ位だったと思う。それと後述するが謎解きが難しいので、その辺をどの程度でクリア出来るかで結構時間は変わってくるだろう。 主人公は二人の様になっているが、実際にプレイヤーが操作するのは常にレナードの方であり、相方のブッバはゴール地点にいて声でそれを知らせる役目でしかない。ゴール地点にいるブッバをCrowbar(カナテコ)でぶん殴るとレベルクリアとなる(つまりシークレット探し等をしたいのならばそこから戻れば良い)。なお彼を殺してしまうとレベルをクリアする事が出来なくなるのでやらないように。 ゲームを評価する上で大きなポイントとなるのが、その独特な雰囲気を気に入るかどうかである。アメリカ南部の片田舎を舞台にしている点からしてユニークだし、地元の新聞を模したヘンテコなマニュアルから、ゲーム内の文章や主人公の喋りには訛りが満載。同エンジン使用のDuke Nukem 3DやShadow Warriorもユーモアを含んだゲームだったが、あくまでも優れた能力を持ったスーパーマン的存在が、ユーモアの要素を併せ持っているという形だった。それに対してこのゲームでは、盗まれた豚を追ってという目的もさることながら、主人公自体が単なる酔っ払いの粗忽者という設定。「Yee-Haw !」と叫びながらお調子者の馬鹿が大暴れするゲームとでも言おうか、その風景と同様にユルくておおらかな雰囲気が強い物となっており、地球の平和を守る為にエイリアンを倒さないとならないという緊張感は微塵も感じられない。 ただしそのユーモアは当のアメリカに住んでいる人でないと感覚的に解らない部分も多いのではないかと考えられ、日本ではBuild Engine 四天王の中で人気や知名度では一番下に位置する物となっているが、海外(アメリカ)ではその4本の中ではこれを推すという人もよく見られる。つまり欧州や日本ではその微妙な感覚が掴みきれないので、その分低評価になっているというのはあるだろう。 レベルの構成はアメリカ南部の田舎や郊外をメインにしているが、いかにも南部というロケーションは半分程度であり、他は施設や工場等のインドアとなっている。よって南部風情丸出しという程では無い。それでも他のFPSではお目にかかれない様な場所が含まれているという点が大きな売りになっているのは確かである。 レベルの構造はDN3DやSWの様に、開かない扉等がまず見付かり、それをアンロックする為のアイテムを探してくるという行為の繰り返しという点は一緒。マップのサイズには限界があるので、それを長い時間プレイさせる為に同じ場所を行ったり来たりしながら進めるというのも同じである。そしてこのゲームでは機械を動かしたりスイッチを操作するのに必要という目的でも、探してくるのはキーに統一されている。しかもキーは全て同じ種類で、ゴールドやシルバー等の色分けがされていない。(ロックされた扉に必要なカードと同じ色の差し込み口が付いていたりといったガイドが無い)。キーが必要な場所にはメッセージが出るので、探し出したらそこに持って来て使うという風にするのだが、キーは全部同じ形状なのにアンロックする箇所とは一対一対応なので、先にキーが必要な箇所が複数見付かる構造のレベルとかだと、入手した或る一本のキーで何所が開くのかを総当たりで試す他はなくなる。 ここでの問題はゲーム展開にそれ程大きな変化が無いという所で、最後まで同じ様なキー探しが延々と続くという感が否めない。キーやカードを探してくるという点はDN3DやSWと一緒だが、各種イベントで変化を付けて「魅せる」という工夫が感じられず、レベルのデザインやバリエーションという観点からはこの2作品に劣っていると言えよう。 本家2作品とは異なる点として、ゲームを進行させる為の謎解きが難解な所が挙げられる。DN3DとSWに比較して進行させる為のルートや方法を見付けるのが難しくなっており、個人的にもこのゲームについてはクリアするのに何回かヒントに頼らないとならなかった。理由の第一はキーが黒くて小さいデザインなので、見落とす可能性があるという点。初回探索時は見付けられずに、再度くまなく探し回って「こんな場所に!」という感じでやっと見付かったりする。暗い場所に在ると特にそれが発生し易くなる。 第二に物陰に隠された目立たないスイッチを押さないとならないとか、撃たないと作動させられないスイッチが見付け難い位置に在ったり、見た目として判り難い亀裂が在ってそれを撃って破壊するとルートが出て来るとか、まるでシークレットを探すかの様に目を皿のようにしないとならないケースが出て来る。普段は開かないオブジェクトなのに、その時だけUseで開く場所が在ったりとかも同様。 第三にスイッチをオンにした際に、それで何所が開いたのかが判り難い。非常に遠くの扉が開いていたりもするので、解らない場合にはマップ内全体を探し回る羽目になる。(よって探索時に開かない場所を憶えておくのも重要になる)。 謎解きが難解なの自体は別に良いのだが、それはパズルの設定や解き方が面白いという場合であって、このゲームの様に単なるアイテムやスイッチ探しを困難にしたり、スイッチによって何の関連性も無い離れた場所が開いたりといったやり方は好みでは無い。 レベル構造の方に問題があるケースもある。内部が非常に複雑な構造のレベルが幾つか含まれており、何所を進んでどういう風にすれば先に進めるのかがあまりに解りにく過ぎてストレスの元になっている。迷路構造その物もたまに出て来るが、こちらはオートマップ機能があるのでまだ救われており、マップを表示した状態で進めれば大分楽にはなる。 内部探索については他のBuild Engineと同じ特徴として、上下方向への視点移動に制限が在るのでパイプの様な狭い通路を上下移動するのはやり難い。また水面から潜れるのかどうかは実際に下降操作をしてみないと判らないという風になっている。他には爆発させる事で周囲のオブジェクトを破壊可能な事があったり、押す事で動かせるオブジェクトも用意されている。 タイミングを要するアクションを要求されるシーンは少ないが、その代わりに要求されるシーンはほぼ全て難易度が高くなっている。例えば動く障害物に接触せずに移動するシーンでは当たり判定の幅がかなり大きいので避けられる距離間を掴むのに苦労するし、ジャンプして渡って行かないとならない場所では精巧なジャンプが要求されてくる。 |

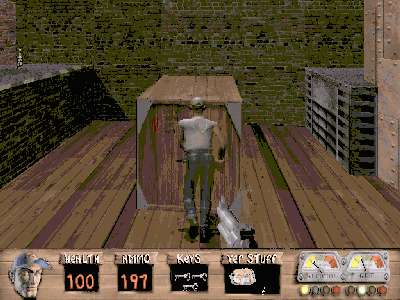
| BASICS |
*武器は全て携帯可能 *三人称視点にも切り替えられる(実用的では無い) *照準のサイズは固定 *マウスの上下動作反転機能は最初から持っている *リロード動作はあるなら自動的に入り、操作にリロードキーは無い *Runモードへの切り替えが可能で、物凄い速さでスタミナを気にせず幾らでも動き回れる *ハシゴを使えるが、操作はジャンプキーで一段ずつ上るような動きとなる *スクリーンサイズは調整可能で、デフォルトでは表示されている下段のステータスを消す事も出来る 特殊アイテムとしては、ヘルスの上限+100を超えて+50の回復が可能なGoo Goo Cluster(鶏肉の固まり), 水中で自動的に使用されるVacuum Hose, ぬかるみを速度低下無しに移動可能なHip wadersが用意されている。 戦闘における最大の特徴がヘルスの回復システムである。先に特殊例から説明しておくと、トイレで小便をすると+10, 「Yee Haw」と叫ぶと+1分のヘルスを回復出来る。ただしこれ等は連続しては行えない。 ヘルスを回復するアイテムは4つ。Pork Rings以外はアイテムとして携帯する事が出来る。 ・Pork Rinds +30 ・CowPie 6切れセット +5/個 ・Whisky 10杯分 +10/杯 ・Beer 6缶セット +5/本 ポイントは画面右下に表示されている二つのメーターで、DRUNKOMETERは酔い加減を、GUTOMETERは満腹度を示している。ウイスキーかビールを飲むとDRUNKOMETERが上昇していき、ポークかパイを食べるとGUTOMETERが上昇する。まずアルコールの方はグリーンまでは問題無いのだが、オレンジまで達してしまうと方向キーの入力が時々おかしくなり、主に真っ直ぐに進めずに斜め方向へと移動がズレてしまう様になる。更に赤になると完全に移動キーの入力が変になって、視界も傾いてボケたように見え難くなり、武器や照準の表示も消えてしまう。そしてMaxまで行くとゲロを吐いて倒れ、その場でしばらく動けなくなる。 Gutの方は上昇すると共に、主人公が放屁やゲップをする様になる。これが何に影響するのかというと、このゲームでは当時のシンプルなアクションFPSとは違って、“向き”という設定が用意されている敵が居る。普通は検知エリア内に入った時点で敵は必ずプレイヤーの存在に気が付いて攻撃してくるようになっているが、このゲームでは「向きが設定されている敵の後方から近付く際には気が付かれないので有利」というシステムが組み込まれている。ところがメーターが上昇しているほどオナラとゲップの音で気が付かれる可能性が高くなってしまうという意味。なおこちらの方は酒類に比較して入手量が少ないので、限界まで食べるとどうなるのかは検証していない。 ステルスの方は少なくとも難易度Meejumでは特に気にする程の物でもなく、ブーブーと屁をこきながら戦っていても問題は無い。実質重要となるのは酒による酔いをどう制御するかである。このメーターを下げる方法だが、両方共に時間経過で自然に減少はしていく。しかし酔いの方は醒めるのが非常に遅く、多分10分以上放っておかないとグリーンまで戻らない。よってオレンジレベルまで飲んでは駄目という話になる。 完全にリセットされるのはレベルが変わった時。自発的に戻す方法としては、ポークかパイを食べるとやや針が戻るようになっている。よって酒とパイを両方携帯している際には、酔いのレベルがグリーン以下に収まるように両者の摂取量を調整しながらヘルスを回復させるという行為が必要になってくる。しかし用意されている数は酒類の方が格段に多い為に、回復アイテムは持っているのに酔いが回ってしまうのでこれ以上は回復出来ないというシチュエーションに悩まされる事が多くなっている。 同じく定期的に酒を摂取するというマネージメントも要求される。これでは危ないという段階になってから一気に飲んだ場合、その酔いはかなり長い時間醒めない。よってそのまま進めてすぐにまたダメージを受けた場合、酒類しかないとグリーン以下に収める為には十分に回復させられないという状況が発生する。そこでメーターに常時注意しながら、徐々に酒を摂取して酔いのレベルをコントロールするのが重要という意味である。 ではなるべく酔いのメーターは下げておく(なるべく食物の方で回復させる)ようにした方が良いのかと言うとそうではない。更に厄介なシステムとしてこのメーターが一種のアーマーの役割を果たしており、両方共にグリーンになっている時が最も敵の攻撃に対して防御力が増すようにされている。つまりグリーンにしておくのが一番効果的だが、そうするとダメージを喰らった時に十分な回復が出来ない恐れがある。逆にメーターが下がった状態では、アーマー値が低いので戦闘時に不利というシステム。 これに関して重要となるアイテムがMoonshine。これは一本だけ携帯可能な使い切りアイテムで、効果発動中は高速で移動が可能というのが基本機能。戦闘時だけでは無く、難易度の高い大ジャンプを簡単にしたり、シークレットに達する為のジャンプを実現したりにも有用となる。だがRunモードにする事でも高速移動は出来るので、その面での有り難みはあまり感じられない。むしろこれを飲んだ後に両方のメーターがリセットされるという効果が一番の役割であり、酒類しか持っていないが大幅にヘルスを回復させたいという時に重宝する。 |